[コラム]千葉県における外来種キョンの拡大と環境への影響
2025.04.22
千葉県における外来種キョンの拡大と環境への影響
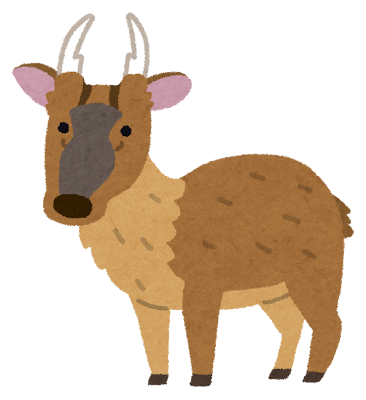
千葉県では、外来種である「キョン」が急速に増加しており、地域の農業や自然環境に影響を及ぼしています。キョンは中国や台湾原産の小型のシカで、日本国内では本来見られない動物ですが、現在では房総半島を中心に生息域を拡大し続けています。
本記事では、キョンの特徴や拡散の経緯、及び現在の被害状況と対策について解説します。
キョンの特徴と日本における由来
キョン(学名:Muntiacus reevesi)は、体長約1メートル、体高約50センチ、体重10〜15kgの小型のシカで、オスには短い角が見られます。雑食性であり、葉や果実、草花などを食べます。
日本には1960年代に観賞用として持ち込まれ、千葉県館山市の動物園で飼育されていましたが、施設の閉鎖や柵の破損などにより一部が逸出。その後、野生下で繁殖し、現在に至っています。
キョンがもたらす環境問題
農作物への被害
キョンは農地に侵入し、葉物野菜や果実を食べてしまうことがあります。特に体が小さいため、従来のシカ向けの防護柵では侵入を防ぎにくく、農家にとって深刻な被害につながっています。
生態系への影響
在来植物がキョンの採食によって減少し、結果として昆虫や小動物にも影響が及ぶとされています。生物多様性の観点からも、地域生態系への長期的な影響が懸念されています。
個体数の増加
天敵が存在しないことや適応力の高さにより、野外での個体数が急増しています。千葉県によると、2023年時点での推定個体数は6万頭を超えており、増加傾向が続いています。
千葉県の対策と今後の課題
捕獲・駆除の強化
千葉県はキョンを「特定外来生物」に指定し、罠の設置やハンターによる捕獲を進めています。また、農家に対しては防護柵の設置支援も行われています。
対策の難しさ
キョンは警戒心が強く、夜間に活動することから捕獲が難しいとされています。また、住宅地に出没するケースもあり、安全面での配慮が必要です。さらに、動物福祉の観点から、過度な駆除に対する懸念の声もあります。
外来種問題としての位置づけ
キョンの増加は、地域限定の問題ではなく、日本全体で注視すべき外来生物問題の一例といえます。環境省では、生態系保全の一環として外来種対策を重要課題としています。
外来種の拡散防止には、地域住民・行政・専門機関が連携して、早期発見・通報・対策を進める体制が不可欠です。
私たちにできること
- 通報の協力:キョンを目撃した際は、自治体や関連機関への通報が求められます。
- 外来種に関する理解の促進:学校や地域活動を通じて、外来種問題についての理解を深めましょう。
- 適切な飼育管理:ペットなど外来動物が自然に放たれないよう、飼育者自身の責任も重要です。
まとめ
キョンの拡大は、農業・環境・地域社会に多方面の影響をもたらしています。個体数の抑制には行政の取り組みだけでなく、地域住民の協力と理解が欠かせません。
持続可能な自然環境を守るためにも、一人ひとりが関心を持ち、適切な対応が取れる社会づくりが求められています。
参考:特定外来生物 キョン

